住宅ローン申し込みの流れとは?必要書類や注意点も解説
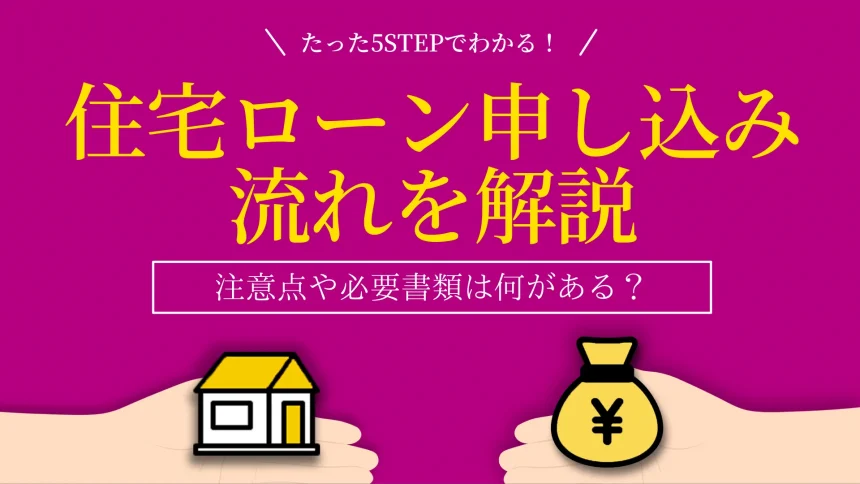
住宅ローンとは、住宅を購入する際に、銀行や金融公庫などの金融機関からお金を借りる仕組みのことです。
住宅ローンは、借りるお金が高額になるため、手続きが複雑で時間と手間もかかります。実際に申し込みをするとなると、何から始めたら良いのか、流れが分からないという方もいるでしょう。
ここでは、住宅ローンの申し込みから融資実行までの流れを分かりやすく解説します。

必要な書類や注意点も紹介しますので、最後まで読んで参考にしてみてくださいね。

監修者
小島 薫
【専門分野】金融業・不動産業
【得意分野】
BtoC:ファイナンシャルプランニング及び金融商品・不動産のコンサルテーション業務
BtoB:不動産事業とのアライアンス業務
【所属組織・役職】
株式会社フォーメンバーズ
ネットワーク加盟事業本部 事業本部長
【保有資格】
日本FP協会認定Certified Financial Planner
国家資格1級ファイナンシャル・プランニング技能士
国家資格 宅地建物取引士
国家資格 賃貸不動産経営管理士
平成8年3月専修大学法学部法律学科卒業後、陸上自衛隊松戸駐屯地勤務。前期教育隊中隊長賞、後期教育隊教導隊長賞など優秀な成績を収める。
訓練の日々に人と接しながら人の役に立つ仕事がしたいと思い、平成11年4月改めて郵政省へ転職。郵便局の内勤事務にて郵政3事業(郵便・貯金・保険)に携わる。窓口業務の傍ら営業の楽しさに目覚め、簡易保険事業の優秀な営業スタッフが目指す、最高優績者表彰、国際優績者表彰受賞するまでとなる。郵政民営化、リーマンショックの際、さらにステップアップしたいと考え平成20年1月外資系銀行へ転職。リテール部門にて特別賞を受賞するなど優秀な成績を収める。
ヘッドハンティングを経て平成21年7月より現株式会社フォーメンバーズにて金融機関窓口セールスの営業力向上のコンサルティングを行うシニアコンサルタントとして活躍。現場スタッフとのコミュニケーションを大切にした手法にて講話、OffJT、OJT、仕組みづくりなどを行い、売上対前年比最大700%を達成するなど数々の実績を誇る。
新興系の銀行に対して、住宅ローン推進におけるコンサルティングをしたつながりにより、イオングループによる不動産仲介業ブランドである「イオンハウジング」立ち上げに関わる。現在はイオンハウジングネットワーク加盟事業本部の責任者として加盟店の運営・拡大に尽力している。
▶CFP®︎認定者資格証明書はこちら
▶宅地建物取引士資格証明書はこちら

監修者
田口 宗勝
【専門分野】不動産ファイナンス・不動産評価
【得意分野】マーケティング戦略・プロジェクト管理
【所属組織・役職】
株式会社フォーメンバーズ
資産管理事業部
アセットマネジメント部門 課長
【保有資格】
宅地建物取引士
平成6年、武蔵大学を卒業後、旭ダイヤモンド工業(株)に入社。名古屋支店に配属され、中部エリアの自動車関連工場の営業担当として活躍をする。
そこでトヨタのカイゼンシステムを実際に体験し、業務効率化に対する熱い関心を抱く。
しかし、平成7年に起きた阪神・淡路大震災の前日、神戸旅行の予定を胸騒ぎによりキャンセル。この予感が的中し、奇跡的に災害から免れる。この経験から、人生を大切にする決意を固め、いつ死んでも後悔のない人生を送ることを決心する。
その後、札幌のハウスメーカーであるコスモ建設(株)でマネージメントの修行を始める。実際の現場で働きながら、リーダーシップの重要性や効果的な指導法を学ぶ。従業員たちを鼓舞し、モチベーションを高める方法や組織全体を一丸として最高のパフォーマンスに導く手法を体得。現場の実践を通じて、人々を動かし、組織を成長させるために必要なスキルや知識を身につける。
平成13年には、パンダ不動産を創業し、時代の先駆者として注目を浴びる。インターネットを活用した収益物件の全国販売に成功し、多くの投資家から感謝される存在となる。管理とバリューアップを並行して行い、5年後には高い評価を得て売却する手法を確立する。
さらに、グローバルな不動産投資にも進出し、香港やカナダなどで活躍。幅広い人脈を築いたことから金融サービス業にも進出し、成功を収める。
その後、フリーペーパー発行や無料情報チャンネル開設、地元の地上波テレビへの出演などを通じて、広く知名度を上げる。紹介を中心とした営業スタイルに特化し、多くの人々からの信頼を得ることに成功する。
そして、平成30年には、自身のノウハウを全国に広めるために(株)フォーメンバーズに参加。八丁堀店と市川妙典店の両店舗での店長を経て、現在は資産管理事業部の課長として、アセット マネジメント部門を統括している。さらに、同社のメディア監修も担当。不動産業界に革新的な情報を提供し、多くの人々を魅了している。洗練されたアイデアと緻密な戦略により、常に業界のトレンドを先取りし、最先端の情報を発信しつづけている。
▶宅地建物取引士資格証明書はこちら

執筆者
真壁
不動産購入をしたとき、大体の方が住宅ローンを組みますよね。また、ローンを組むからには金利が低い金融へ融資を受けたいものです。当サイトでは、住宅ローンでおすすめの金融機関を紹介したり、ローンを組む際の注意点等をまとめているので、是非参考にしてみてください。
本コンテンツ内で紹介しているサービスの一部もしくは全てに、広告を含む場合があります。ただ、広告が各サービスの評価に影響をもたらすことは一切ございません。詳しくは、不動産スタディのコンテンツポリシーとコンプライアンスポリシーをご確認ください。
※当サイトの記事は、次の法律・規約その他の法令の定めに則り作成しております。
・景品表示法
・不動産の公正競争規約
目次
住宅ローンを借り入れる流れを5つのステップで解説

- 住宅ローンに関する情報を集める
- 事前審査
- 本審査
- 契約手続き
- 融資実行
まず最初に住宅ローンの流れを5つのステップで紹介します。
ここでは、住宅ローンを申し込む前の準備から、実際に融資を実行されるまでの基本的な流れを見ていきましょう。
STEP①住宅ローンに関する情報を集める
住宅を購入する場合は、住宅を購入するハウスメーカーや不動産会社に、提携する金融機関の住宅ローン「提携ローン」をすすめられることがあります。
提携ローンでは金利の優遇や手続きが早く進むなどのメリットがあるでしょう。しかし、現在はさまざまな金融機関があります。
今では、定型ローンだけではなくネット銀行などの金融機関やローン商品があります。そこで、金利や条件、諸費用といった情報を独自に集めるのも良い方法です。
それ以外にも、仕事などでお付き合いのある金融機関に相談してみるのも良いでしょう。すでに購入したい住宅が決まっている場合には、具体的なアドバイスを期待できます。

複数の金融機関を比較することで、あなたのライフスタイルに合った住宅ローンが見つかる可能性があります。
STEP②事前審査
事前審査(仮審査)とは、本審査の前段階に行われる簡易審査のこと。事前審査は、インターネットなどから申し込みを行うことも可能です。
事前審査では、金融機関に対して申込者本人の収入、配偶者の有無や収入、自己資金(頭金)の有無などの情報を提供します。
- 返済完了時の年齢
(基本的には20歳~80歳までの間での返済期間が基準) - 勤務形態
(正社員が前提で、収入により派遣社員・契約社員でも可能な場合もあり) - 勤続年数
(2年~3年が基準ですが、資格や専門職では例外もあり) - 返済負担率
(年収に対する年間返済額の割合で、30%~35%が限度額の目安) - 事業内容
(法人や個人の経営者は収入以外に経営する会社等の業績も審査対象になります) - 借入申込み金額と頭金
(ローンの総額と頭金の有無、金額などを問われます) - 健康状態
(健康状態は事前審査での重要視されるので要注意)
STEP③本審査
事前審査を通過した後に本審査が始まります。事前審査で承認された場合でも、この本審査で承認が取り消されたり、減額されることもあります。
本審査では、事前審査よりもさらに詳しい審査が行われるため、金融機関に提出しなければならない書類も多くなります。
本審査で承認の取り消しや減額がないようにするには、事前審査で正確な情報を金融機関に提供しておくことが大切です。
また購入希望物件の詳細な情報や団体信用生命保険に加入するためローンを申し込む本人の健康状態も申告の内容に含まれることがあるのが住宅ローンの特徴といえるでしょう。
このため審査期間もやや長く、1週間~2週間程度かかるケースが多いようです。

本審査では職業・収入・健康の安定が大きなポイントとなります。
STEP④契約手続き

本審査を通過して融資の承認が下りると、金融機関と金銭消費貸借契約を結びます。
また、金銭消費貸借契約と同時に担保となる不動産に対して抵当権の設定も行います。ただし、建築中の物件では完成後に設定することが一般的です。
抵当権とは、購入する住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利のことで、いわゆる「担保に取る」ということと同じ意味を示すものになります。

契約手続きは申し込んだ金融機関で行うことがほとんど。指定された書類等に不備のないように気をつけましょう。
STEP⑤融資実行
融資を実行する際には、金融機関から一度申込本人の口座に借入金を振り込み、それと同時に手数料などの経費が引き落とされます。
それから不動産会社や工務店、ハウスメーカーなどの口座に住宅の代金が振り込まれるという流れです。
住宅が完成していない場合など、後で住宅費用を支払う時は、金融機関が住宅資金を引き出せないように設定します。
新居に必要な家財道具や生活費を、住宅ローンから流用することはできません。もしも必要な場合は、住宅ローン先の金融機関に早めに相談しましょう。

住宅ローンで融資された資金は厳しく管理されることを理解しておきましょう。
住宅ローン借り入れの流れにおける必要書類
- 事前審査申込書
- 本人確認書類
- 収入確認書類
- 物件確認書類
それでは次に、それぞれの手続きの際に必要な書類を解説していきます。
手続きの書類に不備があると、融資の実行が遅れるだけでなく、承認されないこともあるので注意しましょう。
事前審査時の必要書類
事前審査の際に必要となる書類は、金融機関や申し込みの内容で異なります。
必ずそれぞれの金融機関で必要な書類を確認してください。
| 種類 | 必要書類の例 |
|---|---|
| 事前審査申込書 | 金融機関の所定の書類 |
| 本人確認書類 |
|
| 収入確認書類 |
|
| 物件確認書類 |
|
それぞれの書類には、取得するタイミングや期限が設けられている場合がありますので注意してください。
本審査時の必要書類

事前審査が通過した後に実施される本審査では、事前審査の書類以外の書類を提出します。
事前審査時で一度提出した書類は、原則として再提出は不要です。
| 種類 | 必要書類の例 |
|---|---|
| 住宅ローン借り入れ申請書 | 金融機関の所定の書類 |
| 保証委託依頼書 | 保証会社利用の際に必要となります |
| 団体信用生命保険申込書 | 団体信用生命保険利用の際に必要となります |
| 本人確認書類 |
|
| 収入確認書類 |
|
| 物件確認書類 (購入する物件により異なります) |
|
本審査で必要な書類も各金融機関や契約内容によって異なります。必ず金融機関にご確認ください。
契約締結時の必要書類
このように、住宅ローンの手続きにはさまざまな書類が必要です。分からないことは金融機関の担当者に相談しましょう。
住宅ローン借り入れの流れにかかる期間

住宅ローンの借り入れに関しては、事前審査から融資の実行までに最低でも約1ヵ月半程度の時間を必要とします。
また、申し込む方の仕事の種類や頭金の有無などでもかかる時間が大きく異なります。
住宅ローンの申し込みは、早めの準備に越したことはありません。なるべく早く金融機関に相談することをおすすめします。

時間に余裕をもって金融機関に相談することで、自分に合った金利を選択できる可能性が高まります。
住宅ローン借り入れの流れのなかで必要な費用
住宅ローンの借り入れの流れのなかで必要になる費用には、以下の4つが挙げられます。
- 融資手数料
- 印紙税
- ローン保証料
- 登記費用
融資手数料
融資手数料とは保険会社や金融機関に支払う事務手数料のことです。
融資手数料に借入額にかかわらず手数料が一律になっている「定額型」と「融資額の2%」のように借入額に応じて手数料が決まる「定率型」の2つに分かれます。
「定額型」では一般的に3〜5万円が、「定率型」では先程のように融資額の2%など金融機関によって異なります。

融資手数料は金融機関によっては、「保証会社手数料」や「融資事務手数料」と表記が異なる場合があります。
印紙税
印紙税とは、契約書に貼る収入印紙のことです。
印紙税は、契約金額に応じて税額が決まります。例えば、融資額1000万円以上5000万円以下の場合の税額は2万円です。
収入印紙を郵便局などで購入し契約書に貼り、消印を押します。住宅ローン契約のタイミングで支払う必要があるため用意しておきましょう。
ローン保証料
ローン保証料は、住宅ローンの返済ができなくなった場合に、契約者に代わって保証会社から金融機関に返済してもらう保証を受けるために支払う費用です。
金額は返済期間と借入額によって異なります。この保証料は借り入れの際に一括支払う「外枠方式」と、返済中の金利に上乗せして毎月支払う「内枠方式」のなかから選ぶことができます。一括払いでは、35年返済の場合は1000万円当たり20万円程度です。
ただし、保証会社による返済後においても返済義務はなくならないため注意が必要です。

最近のネット銀行では、ローン保証料を不要としているところもあります。
登記費用

抵当権を登記する際に、登録免許税と司法書士に対する手数料が必要になります。
住宅ローン借り入れる流れでの注意点
住宅ローンはマイホームを購入する際に非常に便利ですが、借り入れる流れにおいて注意点もあります。

住宅ローンを検討中の方は、参考にしてみてください。
- 必ずしも低金利が良いとは限らない
- 返済が始まってからの方が大変
必ずしも低金利が良いとは限らない
住宅ローンを選ぶ際、できるだけ金利が低いものをと考える人も少なくありませんが、低金利であればあるほどよいとは限らないという点に注意が必要です。

その理由は、現在どれだけ金利が低くても、その状態がいつまでも続くとは限らないからです。
例えば、変動型だと金利が上がるのに伴って返済額も増えていきます。そのため変動型は短期間で返済できる方におすすめされることが多いです。
しかし、住宅ローンは完済するのに30年以上かかるケースが多く、金利変動の影響を受けてしまう可能性があります。
返済が始まってからの方が大変
住宅ローンの借り入れで注意すべきポイントは、ローンの審査に通ることはもちろんですが、実は返済が始まってからの方が大変ということです。
無理な返済計画を立ててしまい、毎月の返済で生活が苦しい、または返済ができなくなるということもあります。
では、実際に住宅ローンを借りる前に知っておくべきポイントを解説します。

住宅ローンの金利には「固定金利型」「変動金利型」「固定金利期間選択型」の3つの型があります。
それぞれの特徴やおすすめの利用法は以下の通りです。
| 金利の特徴 | おすすめの利用法 | |
|---|---|---|
| 固定金利型 | 住宅ローンを完済するまで金利が変動しない | 金利変動の不安がないため、長期間で返済したい方におすすめ |
| 変動金利型 | 定期的な金利の見直しがある | 金利変動のリスクがあるため、短期で返済したい方に向いています |
| 固定金利期間選択型 | 返済開始からの一定期間(3年・5年・10年など)は固定金利を選択し、その後は自動的に変動金利型に移行する | 固定金利期間が短いほど低金利のために、早めの繰り上げ返済を計画している方におすすめ |
あなたが最もメリットを活かせる住宅ローンを選んでください。
また、住宅ローンを取り扱う金融機関は、大きく分けて公的金融機関と民間金融機関の2つに分類されます。
公的金融機関には、国や地方自治体などの機関の他、独立行政法人勤労者退職金共済機構や独立行政法人住宅金融支援機構などがあります。一方、民間金融機関には、銀行や信用金庫などがあります。
| 公的ローン | 民間融資 | |
|---|---|---|
| 審査基準 | 比較的ゆるめ | 比較的厳しい |
| 勤続年数 | 原則規定なし | 最低2〜3年以上(正社員) |
| 年収 | 原則規定なし | 最低200万円〜400万円以上 |
| ローンの取引履歴 | 民間ほど重視しない (直近の3ヶ月間に延滞などがあると不可の可能性あり) | 非常に重視する (過去2年間に2回以上の延滞があると不可の可能性あり) |
| 選択金利 |
|
|
| 借入限度額 |
| 最大1億円 |
| 年齢制限 |
| 65歳 |
| 団体信用生命保険の加入 | 任意で加入 | 必ず加入 |
| 物件の技術基準の審査 | あり | なし |
上記のように、公的と民間それぞれにメリット・デメリットがあります。

金融機関に対して住宅ローンを申し込む場合には、対象となる住宅があなた自身の物件であることが前提となります。
そのために、住宅ローンの対象となる住宅があなたの物件であることを証明しなければなりません。
一方、不動産の売主はお金の入金がないと物件の引き渡しや所有権の変更には応じません。
そこで、このタイミングのずれの問題を解決するため、住宅ローンの融資実行と不動産の所有者名義の変更を同時に行います。
住宅ローンの同時融資の流れ

- 金融機関が「住宅ローン」を実行して、あなたの預金口座に入金
- 上記のあなたの預金口座から、売主に住宅の購入代金を支払い
- 購入した住宅の鍵などを売主から受け取り
- 住宅ローンを融資した金融機関が、司法書士に購入した住宅に抵当権の設定を依頼
- あなたと売主は、司法書士に購入した住宅の所有権移転登記を依頼
- 司法書士が登記所に出向き、所有権の抹消と設定、そして抵当権設定の登記実行
住宅ローンでは、ローンの返済を完済するまでは、あなたの住宅に金融機関が抵当権を掛けます。この抵当権があるうちは、あなたが自由に住宅を売ることはできません。
この手続きにより、もしもあなたがローンを支払えなくなった時のために、抵当権をもつ金融機関があなたの住宅を差し押さえることができるのです。

抵当権を外すには、住宅ローンの残高を一括返済しなければなりません。
もしもローン残高のある住宅を売却しなければならなくなった場合は、まず住宅ローンを組む金融機関に相談してください。

返済途中の住宅ローンを「借り換え」や「住み替え」などの新たなローンへ組み換えできる可能性があります。
借り入れの流れを掴む!おすすめ住宅ローン4選
ランキング根拠はこちらからご覧いただけます。
auじぶん銀行

- ネット銀行ならでは!固定金利も変動金利、共に低金利
「auじぶん銀行の住宅ローン」と、「モバイル」・「でんき」・「ネット」・「TV」をセットで契約すると最大年0.15%の金利引き下げ
- 2023年、オリコン顧客満足度調査「住宅ローン」No.1獲得
auじぶん銀行の住宅ローンは、オリコン顧客満足度調査や、価格.com住宅ローン人気ランキングで1位を獲得。
契約に必要な書類は、撮影してネットからアップロードするだけなので非常に簡単です。また、ネット銀行ならではの金利の低さが大きな魅力です。
| 変動金利(全期間引下げプラン) | 年0.329%(新規借入) |
|---|---|
| 固定金利10年(当初期間引下げプラン) | 年1.275% |
| 固定20年(当初期間引下げプラン) | 年1.825% |
金利引き下げ特典あり!
「auじぶん銀行の住宅ローン」と、「モバイル」・「でんき」・「ネット」・「TV」をセットで契約すると、以下のような金利引き下げのサービスを受けられます。
| au回線 | 年0.07%引き下げ |
|---|---|
| じぶんでんき | 年0.03%引き下げ |
| ネット | 年0.03%引き下げ |
| TV | 年0.02%引き下げ |
どちらも適用された場合、変動金利だと年0.169%での新規借り入れが可能です。住宅ローンの借り入れ額は大きいため、少しの金利の違いで支払う利息が大きく異なります。

auのスマホを使っている方や、じぶんでんきを契約している方は、auじぶん銀行の利用をおすすめします。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。
auじぶん銀行住宅ローンの基本情報
| 金利 |
※J:COM NET優遇割、J:COM TV優遇割、コミュファ光優遇割は適用条件充足後、3ヶ月後から適用開始となります。 ※「auじぶん銀行の住宅ローン」と、「モバイル」・「でんき」・「ネット」・「TV」をセットでご利用いただくと、住宅ローン適用金利から最大年0.15%引下げます。 ※2024/7/7現在 ※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。 金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。 |
| 事務手数料 | 借入金額の2.20%(税込) |
| 保証料 | 無料※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| 繰上げ返済手数料 | 変動金利適用中は、手数料は無料 ※固定金利特約期間中は、手数料33,000円(税込)が必要となります。 |
| 審査期間 | 最短当日中※仮審査の場合 |
出典:公式サイト
PayPay銀行(新規借り入れ)

- 新規借入時の変動金利は0.380%!業界最低水準
- 新規申し込みで、金利最大年0.13%引き下げのキャンペーン実施中!
- 6種類と充実した団信保障
PayPay銀行の金利は、業界最低水準。特に変動金利の場合、0.5%以下と利息を抑えた借入が実現します。
| 変動金利(通常時) 自己資金10%未満 | 0.380% |
|---|---|
| 変動金利(キャンペーン) 自己資金10%未満 | 0.290% |
| 変動金利(キャンペーン) 自己資金10%以上 | 0.250% |
2024年2月現在、変動金利の引き下げキャンペーンを実施中※1。 2024年3月12日(火)までに住宅ローンの事前審査を申し込みのうえ、2024年6月28日(金)までに変動金利で新規お借り入れした人が対象です!
がん保障も充実している団信が魅力!
PayPay銀行の団信は、全部で6種類です。
- 一般団信
- 一般団信プラス(がん先進付き)
- がん50%保障団信
- がん100%保障団信
- がん100%+10疾病保障団信
- ワイド団信
一般団信・一般団信プラス(がん先進付き)・がん50%保障団信の場合は、金利の上乗せなしで契約できます。

家族構成や働き方、申し込み年齢によって、必要な保障を備えられるので、いさという時にも安心です。
PayPay銀行住宅ローンの基本情報
| 金利 |
※いずれも借り換えの場合 |
| 事務手数料 | 借入金額×2.20%(税込) |
| 保証料 | 無料 |
| 繰上げ返済手数料 | 一部無料あり |
| 審査期間 | 1週間程度※仮審査の場合 |
出典:公式サイト
出典:PayPay銀行住宅ローン(2023年1月現在)
※1: 2024年3月12日(火)までに住宅ローンの事前審査を申し込みのうえ、2024年6月28日(金)までに変動金利で新規お借り入れが完了したお客さま
三菱UFJ銀行

- 女性特典あり!出産前~出産後6ヵ月以内の申し込みで金利引き下げ
- 毎月50Pontaポイントが貯まる
- ビックカメラやアート引越センターなどの特典を受けられる!
三菱UFJ銀行では、新規借り入れ時、以下3つの金利タイプから選択できます。
| 変動金利タイプ | 年0.425% ※金利は年0.345%~年0.425%。 適用金利は、お申込内容や審査結果等により決定します。 |
|---|---|
| 固定金利タイプ | 固定3年:0.91% 固定10年:1.25% 固定20年:2.04% |
| 全期間固定金利タイプ | 固定21年〜25年:1.77% 固定26年〜30年:1.87% 固定31年〜35年:1.93% |
女性向けの特典あり!
新規借り入れ時、出産前から出産後6ヵ月以内に申告すると、1年間は年0.2%の金利優遇を受けられます。

2006年3月24日以降の新規借り入れが対象で、保険証や母子手帳での確認が必要です。
共働きが増え、住宅ローンを契約する女性も増加しています。時代に合った嬉しい特典です。
Pontaポイントが貯まる!
三菱UFJ銀行のスーパー普通預金(メインバンクプラス)と併用すると、毎月50Pontaポイントが貯まります。
Pontaポイントはコンビニでの支払いなど汎用性が高く、日常でのお買い物をお得にしてくれるでしょう。
三菱UFJ銀行住宅ローンの基本情報
| 金利 |
※適用金利や引下幅は、お申込内容や審査結果等により決定いたします。 |
| 事務手数料 | 借入金額×2.20%(税込) |
| 保証料 | 無料 |
| 繰上げ返済手数料 | 一部無料あり |
| 審査期間 | 最短翌日※事前審査の場合 |
出典:公式サイト
出典:三菱UFJ銀行住宅ローン(2024年7月現在)
SBI新生銀行

- ライフプランに合わせた4つの金利タイプ!
- 上乗せ金利年0.1%で、ガン保障付団信に加入可能!
- 日本マーケティングリサーチ機構調べのランキングで3部門No.1を獲得※1
SBI新生銀行の住宅ローンは、ライフプランに応じた4つの金利タイプから選択できます。下記では、新規借り入れ時の金利を一部抜粋して紹介します。
| 変動金利タイプ | 変動金利(半年型)タイプ<変動フォーカス>:年0.42% 変動金利(半年型)タイプ:年0.65% |
|---|---|
| 当初固定金利タイプ(10年) | 年1.10% |
| 長期固定金利タイプ(21-25年) | 年1.50% |
| ステップダウン金利タイプ(31-35年) | スタート金利:年1.70% 31~35年目(最終):年0.85% |
「なるべく金利を抑えたい」という方は変動タイプを、「退職後は金利を抑えたい」という方はステップダウンタイプをおすすめします。
イメージ調査で3部門No.1を獲得!
新生銀行の住宅ローンは、日本マーケティングリサーチ機構調べのランキングで1位を獲得しています。
- 金利+諸費用が魅力の住宅ローン
- 借り換えを検討したい住宅ローン
- 総支払額で選びたい住宅ローン
「低金利かつ実績のある住宅ローンを選びたい」という方にも、新生銀行は向いているでしょう。
新生銀行住宅ローンの基本情報
| 金利 |
※2024年2月現在 |
| 事務手数料 | 借入金額×2.20%(税込)※変動フォーカスの場合 |
| 保証料 | 無料 |
| 繰上げ返済手数料 | 一部無料あり |
| 審査期間 | 1週間程度 |
出典:公式サイト
出典:SBI新生銀行住宅ローン(2023年12月現在)
※1 日本マーケティングリサーチ機構調べ 2022年3月期_ブランドのイメージ調査(2022年2月7日~3月9日実施)調査対象者はこちらを参照。比較対象は銀行業売り上げ上位9社。回答者数は140名。
※2 申し込み・契約:2023年12月29日まで
住宅ローン申し込みの流れに関するよくある質問
その特徴の中から、ご自分にあった金融機関をお選びいただくことが大切です。
まとめ
今回は、住宅ローンを申し込む際に必要な書類や流れ、選び方を解説しました。この記事で住宅ローンに関する基礎知識や、ご自分にあった住宅ローンを選ぶコツをおわかりいただけたかと思います。
住宅購入は何度も経験することはないので、住宅ローンシュミレーションを利用して住宅ローンの流れを掴みつつ、あなたのライフスタイルに合った住宅ローンを賢く選んでみてください。
・本記事の内容は、本記事内で紹介されている商品・サービス等を提供する企業等の意見を代表するものではありません。
・本記事の内容は、本記事内で紹介されている商品・サービス等の仕様等について何らかの保証をするものではありません。本記事で紹介しております商品・サービスの詳細につきましては、商品・サービスを提供している企業等へご確認くださいますようお願い申し上げます。
・本記事の内容は作成日または更新日現在のものです。本記事の作成日または更新日以後に、本記事で紹介している商品・サービスの内容が変更されている場合がございます。
・本記事内で紹介されている意見は個人的なものであり、記事の作成者その他の企業等の意見を代表するものではありません。
・本記事内で紹介されている意見は、意見を提供された方の使用当時のものであり、その内容および商品・サービスの仕様等についていかなる保証をするものでもありません。
