住宅ローンの保証料とは?各種支払方法のメリットと計算法を紹介
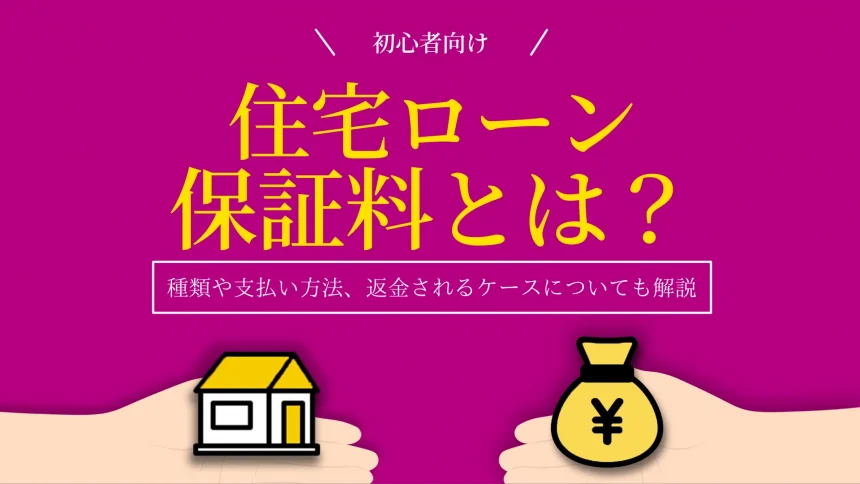
住宅ローンの保証料を実際に知るタイミングは、住宅ローン契約時に提示される諸費用の内訳を見た時が多く、その金額の大きさにちょっと驚いたりしてしまうかもしれません。
しかし一方で、よく聞くフレーズとして「保証料が不要(またはゼロ)」「保証料を比較」「保証料返金」などを耳にします。これはどういうことなのでしょうか?
- 保証料の仕組みについて知りたい
- 保証料の支払いや金額差について知りたい
- 保証料の不要や返金について知りたい
今回は上記の点を踏まえて、住宅ローンの保証料について注意すべきポイントにも言及していきます。

ぜひ今後の住宅ローンを組む際の参考になさってください。

監修者
小島 薫
【専門分野】金融業・不動産業
【得意分野】
BtoC:ファイナンシャルプランニング及び金融商品・不動産のコンサルテーション業務
BtoB:不動産事業とのアライアンス業務
【所属組織・役職】
株式会社フォーメンバーズ
ネットワーク加盟事業本部 事業本部長
【保有資格】
日本FP協会認定Certified Financial Planner
国家資格1級ファイナンシャル・プランニング技能士
国家資格 宅地建物取引士
国家資格 賃貸不動産経営管理士
平成8年3月専修大学法学部法律学科卒業後、陸上自衛隊松戸駐屯地勤務。前期教育隊中隊長賞、後期教育隊教導隊長賞など優秀な成績を収める。
訓練の日々に人と接しながら人の役に立つ仕事がしたいと思い、平成11年4月改めて郵政省へ転職。郵便局の内勤事務にて郵政3事業(郵便・貯金・保険)に携わる。窓口業務の傍ら営業の楽しさに目覚め、簡易保険事業の優秀な営業スタッフが目指す、最高優績者表彰、国際優績者表彰受賞するまでとなる。郵政民営化、リーマンショックの際、さらにステップアップしたいと考え平成20年1月外資系銀行へ転職。リテール部門にて特別賞を受賞するなど優秀な成績を収める。
ヘッドハンティングを経て平成21年7月より現株式会社フォーメンバーズにて金融機関窓口セールスの営業力向上のコンサルティングを行うシニアコンサルタントとして活躍。現場スタッフとのコミュニケーションを大切にした手法にて講話、OffJT、OJT、仕組みづくりなどを行い、売上対前年比最大700%を達成するなど数々の実績を誇る。
新興系の銀行に対して、住宅ローン推進におけるコンサルティングをしたつながりにより、イオングループによる不動産仲介業ブランドである「イオンハウジング」立ち上げに関わる。現在はイオンハウジングネットワーク加盟事業本部の責任者として加盟店の運営・拡大に尽力している。
▶CFP®︎認定者資格証明書はこちら
▶宅地建物取引士資格証明書はこちら

監修者
田口 宗勝
【専門分野】不動産ファイナンス・不動産評価
【得意分野】マーケティング戦略・プロジェクト管理
【所属組織・役職】
株式会社フォーメンバーズ
資産管理事業部
アセットマネジメント部門 課長
【保有資格】
宅地建物取引士
平成6年、武蔵大学を卒業後、旭ダイヤモンド工業(株)に入社。名古屋支店に配属され、中部エリアの自動車関連工場の営業担当として活躍をする。
そこでトヨタのカイゼンシステムを実際に体験し、業務効率化に対する熱い関心を抱く。
しかし、平成7年に起きた阪神・淡路大震災の前日、神戸旅行の予定を胸騒ぎによりキャンセル。この予感が的中し、奇跡的に災害から免れる。この経験から、人生を大切にする決意を固め、いつ死んでも後悔のない人生を送ることを決心する。
その後、札幌のハウスメーカーであるコスモ建設(株)でマネージメントの修行を始める。実際の現場で働きながら、リーダーシップの重要性や効果的な指導法を学ぶ。従業員たちを鼓舞し、モチベーションを高める方法や組織全体を一丸として最高のパフォーマンスに導く手法を体得。現場の実践を通じて、人々を動かし、組織を成長させるために必要なスキルや知識を身につける。
平成13年には、パンダ不動産を創業し、時代の先駆者として注目を浴びる。インターネットを活用した収益物件の全国販売に成功し、多くの投資家から感謝される存在となる。管理とバリューアップを並行して行い、5年後には高い評価を得て売却する手法を確立する。
さらに、グローバルな不動産投資にも進出し、香港やカナダなどで活躍。幅広い人脈を築いたことから金融サービス業にも進出し、成功を収める。
その後、フリーペーパー発行や無料情報チャンネル開設、地元の地上波テレビへの出演などを通じて、広く知名度を上げる。紹介を中心とした営業スタイルに特化し、多くの人々からの信頼を得ることに成功する。
そして、平成30年には、自身のノウハウを全国に広めるために(株)フォーメンバーズに参加。八丁堀店と市川妙典店の両店舗での店長を経て、現在は資産管理事業部の課長として、アセット マネジメント部門を統括している。さらに、同社のメディア監修も担当。不動産業界に革新的な情報を提供し、多くの人々を魅了している。洗練されたアイデアと緻密な戦略により、常に業界のトレンドを先取りし、最先端の情報を発信しつづけている。
▶宅地建物取引士資格証明書はこちら

執筆者
真壁
不動産購入をしたとき、大体の方が住宅ローンを組みますよね。また、ローンを組むからには金利が低い金融へ融資を受けたいものです。当サイトでは、住宅ローンでおすすめの金融機関を紹介したり、ローンを組む際の注意点等をまとめているので、是非参考にしてみてください。
本コンテンツ内で紹介しているサービスの一部もしくは全てに、広告を含む場合があります。ただ、広告が各サービスの評価に影響をもたらすことは一切ございません。詳しくは、不動産スタディのコンテンツポリシーとコンプライアンスポリシーをご確認ください。
※当サイトの記事は、次の法律・規約その他の法令の定めに則り作成しております。
・景品表示法
・不動産の公正競争規約
目次
住宅ローンの保証料とは?
住宅ローンの保証料は保証会社に支払う料金のことです。ここでポイントなのは住宅ローンを組んだ金融会社ではなく保証会社であること。
例えば、住宅ローンを組む際に、金融機関から融資の条件として「保証会社と契約してもらう必要がある」ことを伝えられるケースを想定してみましょう。
「なぜ保証会社と契約?」という疑問をいだきますが、答えは簡単。金融機関は利用者が支払い不能になった場合、保証会社から住宅ローンが弁済されるのです。
では具体的に「保証料」とは、住宅ローンのどの項目に属しているのでしょうか?下記で詳しく紹介していきましょう。
保証料は諸費用の中の1つ
保証料は住宅ローンの諸費用の中に含まれます。諸費用とは住宅ローンを契約する際に発生する経費のこと。下記の例をご覧ください。
| 都市銀行から住宅ローン3,000万円を35年返済で借りた場合の一例 | |
|---|---|
| 事務手数料 | 55,000円 |
| 印紙税 | 20,000円 |
| 保証料 | 618,000円 |
| 登記費用 | 100,000円 |
| 合計 | 793,000円 |
返済不能になった際に、保証会社が代わりに弁済
保証料が必要になる時は、住宅ローンを組んだ方は何らかの理由で「返済不能」に陥った時です。このまま返済をしてもらえない場合、金融機関にとっては「貸し倒れ」となり、大きな損失となります。
その貸し倒れのリスクを回避するのが保証料。保証契約をすると、債務者が返済不能の場合、保証会社が債務者に代わって金融機関に住宅ローンの代金を払います。

住宅ローンは年単位の長い返済期間なので、金融機関も不足の事態に備えているわけですね。
債務が免除されるわけでは無い
保証会社から金融会社への支払いは一時しのぎの代位弁済に過ぎず、今度は保証会社から債務者に金融会社に支払った同額分が請求されます(これを求償権と言います)。
ただ、返済不能になっている債務者が、すぐに返済能力を持ち直し保証会社へ返済するケースはあまり現実的ではありません。
そこで、保証会社は住宅ローンを契約時に不動産に抵当権を設定し債務者が返済不能の場合に抵当権を実行、つまり競売にかけて元金に充当する流れを取ります。
住宅ローン保証料の2種類の支払い方法
先述したように保証料は、住宅ローンの諸費用の中で占めるウェイトが高く、住宅ローンを組んだ当初から全額一括で支払うには負担が高いケースもあります。
外枠方式は一括前払いタイプ
外枠方式は、保証料全額を一括払いするタイプ。ローンの支払金額に組み込まれないので外枠方式と呼ばれています。つまり保証料を支払うタイミングは、住宅ローン契約時で前払いとなります。
内枠方式は月の金利上乗せタイプ
内枠方式は、保証料を分割して支払うタイプ。支払うタイミングは月々の住宅ローン返済時で、本来のローン分に上乗せして支払っていきます。この時注意すべきは分割して払う分、利息が発生することです。
外枠方式と内枠方式のメリット・デメリット
では保証料はどちらの支払いタイプを選ぶべきなのでしょうか?そこで、上記を踏まえて、外枠方式と内枠方式のメリット・デメリットをまとめてみました。
| 外枠方式 | 内枠方式 | |
|---|---|---|
| メリット | 保証料の支払い総額は利息が発生せず、内枠方式よりも少なく済む。 | 全額前払いしなくていいので、ローン契約時に諸費用を少なくできる。 |
| デメリット | 全額前払いする必要があるで、ローン契約時に諸費用を多く用意しておかなければならない。 | 住宅ローンが長期になると、利息分の支払いも長くなり、結果支払い総額が外枠方式よりも多くなる。 |
契約時にまとまった資金があれば、いうことはありませんがそれぞれの家庭の事情は様々。どちらが正解ということはありません。ご自身のマネープランに合わせて賢く選択してください。
外枠・内枠方式の支払い総額をシミュレーション
では実際に外枠方式と内枠方式の支払い総額をシュミレーションしてみましょう。不動産価格が3,000万円・返済期間が35年・元利均等方式の条件に設定してみました。
そして基本の金利は全期間固定金利型として1.34%にし、内枠方式はこの金利に保証料分0.2%上乗せ(1.54%)にしています。
| 外枠方式(金利1.34%) | 内枠方式(金利1.54%) | |
|---|---|---|
| 借入額 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 保証料 | 620,000円 | – |
| 毎月返済金額 | 89,522円 | 87,510円 |
| 住宅ローン総支払額 | 38,219,095円 | 38,826,354円 |
外枠方式と内枠方式の合計金額を比べてみると、外枠方式ー内枠方式=607,259円となり、60万円以上の差額となります。
例えば上記条件のまま25年ローンにすれば、その差額が392,035円、15年ローンにすれば、224,825円となります。
つまり、利用者によっては「内枠方式は長期的には痛い出費だけど、中期的返済ではこの程度の費用は許容範囲」、「契約初期に出費せず、手元に資金を残せる」と評価することもできます。
いずれにせよ、どの期間でいくら金額を借りるか?、契約時に手元にある程度の資金が用意できるか?にも左右されます。ケースに応じてご検討ください。

ご自身にとって無理のないプランが一番大切になってきます。
保証料がかからない住宅ローンはある?
保証料がかからないことをうたい文句にしている住宅ローンも多く存在していますよね。特に下記の2点はとても有名です。
- フラット35(住宅金融支援機構+民間金融機関)
- ネット銀行の住宅ローン
では保証料がかからない両者について、下記で詳しく紹介していきます。住宅ローン利用者にとっては、諸費用全体を抑えることにつながりますので要チェックです!
フラット35(住宅金融支援機構+民間金融機関)
フラット35は、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携している住宅ローン。全期間固定金利という特徴があり、保証料が不要で有名な金融商品です。
フラット35は、利用者が住宅ローンの資金を受け取った後、住宅金融支援機構が住宅ローンの貸し手の民間金融機関から住宅ローンを買い取る仕組み。
ただ、(融資)事務手数料は契約した民間金融機関によって発生します。具体的な金額はその金融機関次第になりますのでご注意ください。

国がバックボーンにあるから経営地盤は安泰なのですね。
ネット銀行の住宅ローン
保証料ゼロでしかも手数料も安いネット銀行も多数あります。中には実際に他の金融機関と比較しても総額数十万円単位で諸費用が浮いて、お得なケースも。
ただ住宅ローンの保証料が無料ということは、ネット銀行は保証会社を通さないことであり、利用者が返済不能になった場合、貸し倒れリスクを負うことを指します。

本記事でもおすすめ銀行サイトでご紹介しています。
住宅ローンの保証料が返金される2つのケースとは
費用が高くて負担になりがちな保証料ですが、下記の2つのケースに当たる場合には保証料が返金されることがあります。
- 外枠方式であること
- 繰り上げ返済時や借り換え時であること
繰り上げ返済時や借り換え時に保証料が返金となるケースとは?
例えば、返済期間が35年の住宅ローンを組んだ場合を想定してみます。下記のようなケースが保証料の返金に該当します。
返済期間中にまとまった資金ができ、一括で返済したいとなった場合(繰上げ返済)や返済期間中に他の金利の安い金融機関が見つかり、借り換えをする場合(借り換え時)。
当初は35年の返済期間の住宅ローンの保証料に対して前払いをしています。途中解約となれば、35年の期間ではなくなり、途中解約までの期間内の保証料しか発生しないことになりますね。
では保証料はいつ返金されるか?
上記のどちらかの対応になるかは金融機関によって異なりますので、事前にお問い合わせをして確認しておくと安心ですよ。
住宅ローンの保証料について注意すべきポイント
住宅ローンを選ぶ際、保証料が安かったり、不要になったりすれば確かにお得ですが、選ぶポイントはそこだけでいいのでしょうか?
住宅ローンは高い買い物。慎重に慎重を重ねて損と言うことはありません。今回は下記のポイントについてまとめましたので、お知りおきください。
- 保証料分が発生しない代わりに金利などで乗せている場合がある
- 保証料分が発生しない代わりに(融資)事務手数料で費用がかかる場合が多い
保証料が発生しない場合は金利に注意
上記の場合、0.2%の金利が上乗せされているのが基本です。まずはシュミレーションをしてみてお得かどうか判断してみましょう。
保証料が発生しない場合は(融資)事務手数料がかかる場合が多い
もちろん、手数料が数万円程度やキャンペーン中で1%程度の場合も多いので、ネットリサーチする場合は全体の数字を目ざとくチェックするようにしましょう。
【保証料で比較】おすすめ住宅ローン4選
ランキング根拠はこちらからご覧いただけます。
※1:審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。
auじぶん銀行

- ネット銀行ならでは低金利!
- 保証人がいなくても、保証付金利プランで利用可能!
auじぶん銀行では仮審査から契約まで、すべてオンラインで手続き可能です。ネット銀行の強みを活かし、実店舗に必要なコストをカットした分、低金利を実現しています。
以下は新規借り入れ時(全期間引下げプラン)の金利です。
| 変動金利(全期間引下げプラン) | 年0.329% |
|---|
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。
出典:auじぶん銀行住宅ローン(2024年7月現在)
auじぶん銀行住宅ローンの基本情報
| 金利 |
※J:COM NET優遇割、J:COM TV優遇割、コミュファ光優遇割は適用条件充足後、3ヶ月後から適用開始となります。 ※「auじぶん銀行の住宅ローン」と、「モバイル」・「でんき」・「ネット」・「TV」をセットでご利用いただくと、住宅ローン適用金利から最大年0.15%引下げます。 ※2024/7/7現在 ※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。 金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます。 |
| 事務手数料 | 借入金額の2.20%(税込) |
| 保証料 | 無料※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| 繰上げ返済手数料 | 変動金利適用中は、手数料は無料 ※固定金利特約期間中は、手数料33,000円(税込)が必要となります。 |
| 審査期間 | 最短当日中※仮審査の場合 |
出典:公式サイト
PayPay銀行(新規借り入れ)

- 変動・固定両方とも業界トップクラスの低金利
- キャンペーンでさらに金利が下がる特典あり
- 住宅ローン申込ナビが便利
PayPay銀行は、業界最低水準の低金利で住宅ローンを提供しているのが強みです。
| 変動金利(新規借り入れ) | 年0.315% |
|---|---|
| 固定金利10年(新規借り入れ) | 年1.145% |
新規お借入れキャンペーン
新規お借入れキャンペーンとして変動金利で契約すると、通常金利0.380%から0.031%引き下げられた0.349%が適用されます※1。
少しでも低い金利での借り入れを希望している方には、PayPay銀行がおすすめです。
住宅ローン申込ナビが使いやすい
住宅ローン申込ナビに登録すれば、手続きの方法をナビゲートしてもらえます。住宅ローン申込ナビでは以下の機能が利用可能です。
- 審査申込と審査結果の確認
- 団体信用生命保険の申し込み
- 本審査に必要な書類の提出
- 契約書作成依頼
- 振込先登録
- 掲示板機能

手続きが簡単な住宅ローンを探しているという方には、PayPay銀行がおすすめです。
掲示板機能のコンタクトボードを使えば、営業時間外でも問い合わせの書き込みができます。日中は忙しくて時間が取れないという方にも便利です。
PayPay銀行住宅ローンの基本情報
| 金利 |
※いずれも借り換えの場合 |
| 事務手数料 | 借入金額×2.20%(税込) |
| 保証料 | 無料 |
| 繰上げ返済手数料 | 一部無料あり |
| 審査期間 | 1週間程度※仮審査の場合 |
出典:公式サイト
出典:PayPay銀行住宅ローン(22024年3月現在)
三菱UFJ銀行

- 「スマート手続」利用者は金利が優遇
- 借入時の保証料は不要
- 家電購入特典・引越特典・女性向け特典など特典が盛りだくさん
三菱UFJ銀行では、店頭窓口での申し込みに加えて、手続きがネットで完結する「スマート手続」を採用しています。
スマート手続を利用すると、通常より金利が優遇。現在は、以下のような金利で借り入れが可能です。
| 変動金利タイプ | 年0.425%※金利は年0.345%~年0.425%。適用金利は、お申込内容や審査結果等により決定します。 |
|---|---|
| 固定金利タイプ | 固定10年:1.25%〜1.33% |
借入時に必要な事務手数料は、借入金額の2.2%。保証会社を利用した住宅ローン契約の場合でも、保証料は必要ありません。
住まいと家族を守れる保険サービス
三菱UFJ銀行の住宅ローンは、住まいと家族の未来を守れる保険サービスが充実しているのも、大きな特徴です。
7大疾病保障付住宅ローンビッグ&セブン〈Plus〉や、健康上の理由で従来の団体信用生命保険へ加入が認められない方のために引受範囲を広くしたワイド団信などがあります。

年齢や既往歴・予算や希望する保障の範囲などを考慮して、ニーズに合った保険に加入できるでしょう。
特典が盛りだくさん
借入金額1,000万円以上・借入期間10年以上の住宅ローン新規契約者は、家電購入特典・引越特典、ホームセキュリティ特典が受けられます。
住宅ローンを借りている本人から出産前・出産後6か月以内に、出産予定もしくは出産があったという申し出があると、そこから1年間適用金利より年0.2%金利が優遇されます。

さらに、借入期間中はPontaポイントが、毎月50ポイント付与されます。
三菱UFJ銀行住宅ローンの基本情報
| 金利 |
※適用金利や引下幅は、お申込内容や審査結果等により決定いたします。 |
| 事務手数料 | 借入金額×2.20%(税込) |
| 保証料 | 無料 |
| 繰上げ返済手数料 | 一部無料あり |
| 審査期間 | 最短翌日※事前審査の場合 |
出典:公式サイト
出典:三菱UFJ銀行住宅ローン(2024年7月現在)
SBI新生銀行

- ライフプランに合わせて、4つの金利タイプから選べる
- 金利・事務取扱手数料が優遇されるキャンペーン実施中
- 保証会社を利用しないので保証料の負担なし
SBI新生銀行の住宅ローンは、変動金利・当初固定金利・長期固定金利・ステップダウンという、4種類の金利タイプがあります。
特徴を把握しライフスタイルや、返済プランに合った金利タイプを選べる点が魅力です。
保証料の負担なし
新生銀行のパワースマート住宅ローンでは、保証会社という仕組みは利用していません。保証料を負担することはありません。
申込者に死亡や高度障害といった不測の事態が起こった場合は、団体信用生命保険で保障されます。

一般団信への加入は0円、ガン団信へは金利に0.1%上乗せすることで加入できます。
新生銀行住宅ローンの基本情報
| 金利 |
※2024年2月現在 |
| 事務手数料 | 借入金額×2.20%(税込)※変動フォーカスの場合 |
| 保証料 | 無料 |
| 繰上げ返済手数料 | 一部無料あり |
| 審査期間 | 1週間程度 |
出典:公式サイト
出典:SBI新生銀行住宅ローン(2024年3月時点)
住宅ローンの保証料に関するよくある質問
保証料は保証会社と利用者が直接契約をするのですが、手数料は金融機関が保証料を負担する形をとっていることです。
また、手数料タイプは金融機関によっては返金の対応をしていない場合があるのでご注意ください。
違います。団体信用生命保険は不慮の(死亡)事故や病気に対して、今後支払い能力が見込めない場合は支払い不能時に代位弁済してくれる保険です。
対して保険料は上記の条件に該当しても求償権は残ってしまいます。団体信用生命保険は個別に検討するべき保険と言えるでしょう。
まとめ
住宅ローンを組む際によく金利にばかり目がいきがちですが、保証料もプランを検討する際に見逃せない要素であることがご理解できたと思います。
ただ、保証料が安くなっていたり、ゼロになっていても、落とし穴が潜んでいるかもしれないので注意が必要です。下記のようにくまなく点検してみましょう。
- 保証料が発生するか?
- 保証料が発生する場合の支払い方法(外枠か内枠か)は?
- 保証料が発生しない場合、他の諸経費(事務手数料など)はどうか?
- 保証料が発生する場合としない場合、総合的にお得な方はどちらか?
具体的には、ネットのシミュレーションや銀行からの見積もりなどがおすすめ。うまく活用しながら、住宅ローンのトータル金額で総合評価するようにしましょう。
・本記事の内容は、本記事内で紹介されている商品・サービス等を提供する企業等の意見を代表するものではありません。
・本記事の内容は、本記事内で紹介されている商品・サービス等の仕様等について何らかの保証をするものではありません。本記事で紹介しております商品・サービスの詳細につきましては、商品・サービスを提供している企業等へご確認くださいますようお願い申し上げます。
・本記事の内容は作成日または更新日現在のものです。本記事の作成日または更新日以後に、本記事で紹介している商品・サービスの内容が変更されている場合がございます。
・本記事内で紹介されている意見は個人的なものであり、記事の作成者その他の企業等の意見を代表するものではありません。
・本記事内で紹介されている意見は、意見を提供された方の使用当時のものであり、その内容および商品・サービスの仕様等についていかなる保証をするものでもありません。
