壁紙リフォームの費用相場は?種類や選び方・注意点まとめ
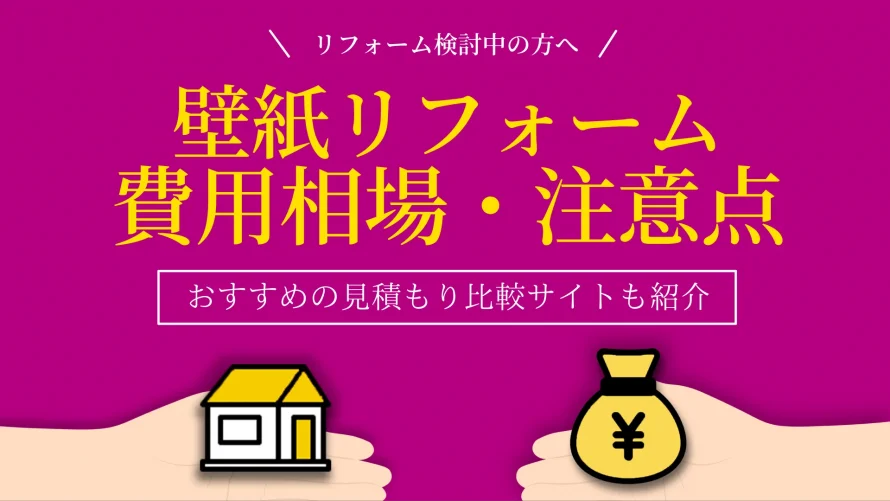
「壁紙のリフォームにかかる費用が知りたい」「リフォームしたいけれどどんな壁紙を選べばいいかわからない」こういった思いや疑問を抱く人も多いのではないでしょうか。
壁紙は種類によって費用相場が異なり、壁紙を購入する以外の諸費用も必要です。リーズナブルな価格帯で希望に合ったリフォームを実現させるためには、壁紙リフォーム事情を把握しておくことが大切です。
把握しておけば、発注後に後悔してしまう確率を下げられるかもしれません。この記事では、壁紙リフォームの費用相場と選び方や注意点について詳しく解説。
また壁紙リフォーム会社が探せる、おすすめリフォーム見積もり比較サイトも5社厳選し紹介します。


監修者
小島 薫
【専門分野】金融業・不動産業
【得意分野】
BtoC:ファイナンシャルプランニング及び金融商品・不動産のコンサルテーション業務
BtoB:不動産事業とのアライアンス業務
【所属組織・役職】
株式会社フォーメンバーズ
ネットワーク加盟事業本部 事業本部長
【保有資格】
日本FP協会認定Certified Financial Planner
国家資格1級ファイナンシャル・プランニング技能士
国家資格 宅地建物取引士
国家資格 賃貸不動産経営管理士
平成8年3月専修大学法学部法律学科卒業後、陸上自衛隊松戸駐屯地勤務。前期教育隊中隊長賞、後期教育隊教導隊長賞など優秀な成績を収める。
訓練の日々に人と接しながら人の役に立つ仕事がしたいと思い、平成11年4月改めて郵政省へ転職。郵便局の内勤事務にて郵政3事業(郵便・貯金・保険)に携わる。窓口業務の傍ら営業の楽しさに目覚め、簡易保険事業の優秀な営業スタッフが目指す、最高優績者表彰、国際優績者表彰受賞するまでとなる。郵政民営化、リーマンショックの際、さらにステップアップしたいと考え平成20年1月外資系銀行へ転職。リテール部門にて特別賞を受賞するなど優秀な成績を収める。
ヘッドハンティングを経て平成21年7月より現株式会社フォーメンバーズにて金融機関窓口セールスの営業力向上のコンサルティングを行うシニアコンサルタントとして活躍。現場スタッフとのコミュニケーションを大切にした手法にて講話、OffJT、OJT、仕組みづくりなどを行い、売上対前年比最大700%を達成するなど数々の実績を誇る。
新興系の銀行に対して、住宅ローン推進におけるコンサルティングをしたつながりにより、イオングループによる不動産仲介業ブランドである「イオンハウジング」立ち上げに関わる。現在はイオンハウジングネットワーク加盟事業本部の責任者として加盟店の運営・拡大に尽力している。
▶CFP®︎認定者資格証明書はこちら
▶宅地建物取引士資格証明書はこちら

監修者
田口 宗勝
【専門分野】不動産ファイナンス・不動産評価
【得意分野】マーケティング戦略・プロジェクト管理
【所属組織・役職】
株式会社フォーメンバーズ
資産管理事業部
アセットマネジメント部門 課長
【保有資格】
宅地建物取引士
平成6年、武蔵大学を卒業後、旭ダイヤモンド工業(株)に入社。名古屋支店に配属され、中部エリアの自動車関連工場の営業担当として活躍をする。
そこでトヨタのカイゼンシステムを実際に体験し、業務効率化に対する熱い関心を抱く。
しかし、平成7年に起きた阪神・淡路大震災の前日、神戸旅行の予定を胸騒ぎによりキャンセル。この予感が的中し、奇跡的に災害から免れる。この経験から、人生を大切にする決意を固め、いつ死んでも後悔のない人生を送ることを決心する。
その後、札幌のハウスメーカーであるコスモ建設(株)でマネージメントの修行を始める。実際の現場で働きながら、リーダーシップの重要性や効果的な指導法を学ぶ。従業員たちを鼓舞し、モチベーションを高める方法や組織全体を一丸として最高のパフォーマンスに導く手法を体得。現場の実践を通じて、人々を動かし、組織を成長させるために必要なスキルや知識を身につける。
平成13年には、パンダ不動産を創業し、時代の先駆者として注目を浴びる。インターネットを活用した収益物件の全国販売に成功し、多くの投資家から感謝される存在となる。管理とバリューアップを並行して行い、5年後には高い評価を得て売却する手法を確立する。
さらに、グローバルな不動産投資にも進出し、香港やカナダなどで活躍。幅広い人脈を築いたことから金融サービス業にも進出し、成功を収める。
その後、フリーペーパー発行や無料情報チャンネル開設、地元の地上波テレビへの出演などを通じて、広く知名度を上げる。紹介を中心とした営業スタイルに特化し、多くの人々からの信頼を得ることに成功する。
そして、平成30年には、自身のノウハウを全国に広めるために(株)フォーメンバーズに参加。八丁堀店と市川妙典店の両店舗での店長を経て、現在は資産管理事業部の課長として、アセット マネジメント部門を統括している。さらに、同社のメディア監修も担当。不動産業界に革新的な情報を提供し、多くの人々を魅了している。洗練されたアイデアと緻密な戦略により、常に業界のトレンドを先取りし、最先端の情報を発信しつづけている。
▶宅地建物取引士資格証明書はこちら

執筆者
真壁
不動産売却を決めたけど、次はどうしたらいいんだろうと悩んでいませんか?実は、不動産売却を考えたら、次のステップは不動産の一括査定サイトを使うことになります。不動産がいくらで売れるかは選んだ不動産会社次第になりますが、不動産一括査定サイトを利用することで不動産会社選びに失敗するリスクをおさえることができ、おすすめです。
本コンテンツ内で紹介しているサービスの一部もしくは全てに、広告を含む場合があります。ただ、広告が各サービスの評価に影響をもたらすことは一切ございません。詳しくは、不動産スタディのコンテンツポリシーとコンプライアンスポリシーをご確認ください。
※当サイトの記事は、次の法律・規約その他の法令の定めに則り作成しております。
・景品表示法
・不動産の公正競争規約
目次
壁紙リフォームの費用相場
| 部屋の広さ | スタンダードグレード | ハイグレード |
| 4.5畳(約8.28㎡) | 3万~ | 5万~ |
| 6畳(約9.93㎡) | 4万~ | 5.6万~ |
| 8畳(約13.24㎡) | 4.6万~ | 6.5万~ |
| 10畳(約13.31㎡) | 5万~ | 7.3万~ |
| 12畳(約19.86㎡) | 5.7万~ | 7.9万~ |
壁紙リフォームの費用は、「壁紙(クロス)の料金+施工費用」で決まり、種類はシンプルなスタンダードグレードと、多様なデザインと機能のハイグレードがあります。
スタンダードグレードの費用は1㎡あたり800~1000円程でハイグレードの場合は1000円~1500円程です。
壁紙の購入代金とは別に、工事費と古い壁紙の処分費用、下地処理費、養生費用などもかかります。

| おすすめ 見積もり比較サイト | リショップナビ | ホームプロ | ハピすむ |
|
|  | |
| おすすめ ポイント | ・リアル口コミが見れる ・指名見積もりができる | ・匿名&完全無料 ・しつこい営業なし営業電話はなし! | ・利用実績25万件以上 ・サービス満足度94%以上! |
| 加盟社数 | ◎ | 全国約1,200社 | 全国約1,000社 |
| 特典 | ・お祝い金最大30,000円分プレゼント! ・工事完成保証が無料で付帯 | ・工事完成保証が無料で付帯 | ・補助金として10万円分プレゼント |
| 公式 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
一括見積もりサイトのランキング根拠はこちらです。
リショップナビ

- リショップナビ安心保証でリフォームにありがちなトラブルを防止
- カスタマーサポートが希望に合ったリフォーム会社を紹介してくれる
- 最大で3万円分のAmazonギフト券がもらえる
- 最大5社から見積もりをもらえる
- 独自の厳しい加盟基準を設けて紹介する会社を厳選している
リフォームでは、工事を依頼した会社が倒産するトラブルがしばしば起きています。リフォーム会社が倒産すると、契約金は返ってこないしリフォームも完成しません。
そこでリショップナビは、リフォーム会社が倒産してしまった場合に備えた「リショップナビ安心保証」という制度を用意しています。
見積もりを申し込むとリショップナビのカスタマーサポートが、提携している1,400社から希望に合ったリフォーム会社を紹介してくれます。
リショップナビで紹介された会社とリフォーム工事の契約をしてアンケートに回答したら、最大で3万円分のAmazonギフト券がもらえるキャンペーン※も実施中です。
※終了時期未定

- 施工日数: 10日間
- 物件種: マンション・アパート
- リフォーム費用: 約150〜200万円(リビング 、 ダイニング 、 洋室 、 和室)
- 施工会社:株式会社LINK


ホームプロ

- 利用者満足度が90%以上※1
- リフォーム会社を最大で8社紹介してもらえる
- 現地調査までは個人情報を伝えずにリフォーム会社とやりとりできる
- 会員数90万人突破
- サービスの質を向上させるべく提携リフォーム会社に対し指導・育成を行っている
ホームプロは、2001年にサービス開始して以来、多くの人に利用されています。利用者の満足度はなんと90%以上です。
見積もりを依頼すると、リフォーム会社を最大で8社紹介してもらえます。多くの見積もり比較サイトでは最大一括査定業者数は3社なので、見積もりがたくさん欲しい人にはホームプロがぴったりです。
見積もり申し込み後に現地調査を依頼するまでは、マイページ内で匿名にてリフォーム会社とやり取りできます。
現地調査を断りたいときは、マイページで「お断りボタン」を押すだけ。気軽に利用できる見積もり比較サイトです。

- 施工日数: –
- 物件種: マンション
- リフォーム費用: 約24万円(床、クロス張り替え)
- 施工会社: 株式会社ドリームONE


ハピすむ

- リフォームコンシェルジュが希望にぴったりな会社を紹介
- 全国1,000社以上の優良なリフォーム会社と提携
- 土日祝日でもリフォームコンシェルジュが相談に乗ってくれる
- 東証プライム市場上場企業が運営しているから信頼性が高い
- メディア掲載実績があり信頼性が高い
ハピすむは厳正な審査基準をクリアした1,000社以上の優良なリフォーム会社と提携。その中から「リフォームコンシェルジュ」が希望に合ったリフォーム会社を紹介してくれます。
リフォームコンシェルジュは、リフォームスタイリストや福祉住環境コーディネーターなどの資格所有者が多数在籍しています。
ハピすむでは土日祝日もリフォームコンシェルジュが対応しており、疑問や悩みなどを聞いて相談に乗ってくれるので、希望に沿ったリフォームができるでしょう。
また、運営会社の株式会社エス・エム・エスは東証プライム市場に上場しているため、信頼性も高いです。

| 運営会社 | 株式会社エス・エム・エス |
|---|---|
| 利用料金 | 無料 |
| 最大一括査定業者数 | 3社 |
出典:ハピすむ公式サイト
壁紙のリフォームにかかる期間
壁紙のリフォームにかかる期間は、6畳の部屋やトイレなら1日ほど。リビングのように広い部屋なら2日前後かかります。
3LDKの家全体を壁紙リフォームするとなると、1週間〜10日ほどかかるでしょう。
一般的な住宅の壁紙リフォームなら、職人さんは1人〜2人で作業します。住みながら壁紙リフォームすることも可能ですが、念入りな養生用となり作業時間も制限されるため、時間がかかるでしょう。
なるべくリフォームに時間をかけたくない人は、時計など壁についた装飾品を外しておき、移動できる家具やインテリアは別室にどかしておくのがおすすめです。

DIYで壁紙をリフォームする際のポイント
壁紙の張り替えは比較的ハードルが低く、DIYする人も多くいます。
壁紙には裏面にのりが付いているものもありますが、今回はのりなしタイプの壁紙を使ってDIYでリフォームする方法を紹介します。
リフォームに必要なものを揃える
- 壁紙
- 下地用のパテ
- 左官ゴテ
- 地ベラ
- なでバケ
- クロス用ヘラ
- カッター、ハサミ
- やすり
- のり
- ローラー
- バケツ
- 脚立
- ぞうきん
- メジャー
- ビニールシート、養生シート
上記はDIYでの壁紙リフォームに必要なものです。
下地用のパテは、古い壁紙を剥がした後にボードの継ぎ目や凸凹を埋めるための材料です。左官ゴテは、下地をパテで補修するときに使います。

地ベラは壁紙をカットするときに使いますが、定規でも代用可能です。なでバケは壁紙を貼ったあとにシワを伸ばしたり空気を抜いたりするのに、クロス用ヘラは角に折り目をつけるために使います。
のり塗るとき用に、ローラーやバケツも用意しましょう。カッターやはさみ、脚立、ぞうきん、メジャーは自宅で普段使っているようなもので大丈夫です。養生シートは壁や家具などを汚さないために使います。
DIYで壁紙を貼る手順を認識する
- 古い壁紙を剥がす
- 下地を処理する
- 養生する
- 壁紙を貼る
DIYでの壁紙リフォームは大まかにこのような流れで進みます。
まずは古い壁紙を剥がし、下地ボードの隙間や凸凹なところにパテを塗って下地補修しましょう。パテが乾いたら、やすりをかけて平らにします。

次に、周辺の壁紙や家具を養生し、床にはビニールシートを敷きましょう。壁紙をカットして裏面にローラーでのりを塗ったら、壁に貼り付けます。
端の方から空気を押し出すようにするのがポイントです。壁紙の上に少し被せるように隣にも壁紙を貼っていきます。最後に壁紙の継ぎ目をヘラでしっかり押さえて余分な部分はカットしましょう。

DIYとリフォーム業者のメリット・デメリットを把握しておく
DIYは、工事代などがかからないため安くリフォームできることがメリットです。
しかし、壁紙を上手に貼るのは意外とテクニックがいるものです。美しく仕上げたいなら、やはりプロであるリフォーム会社に頼んだ方がいいでしょう。

また、壁紙のリフォームではさまざまな道具を用意しなくてはいけません。
普段からよくDIYするのであればいいかもしれませんが、そうでなければ滅多に使わないのに購入するのはもったいないので、リフォーム会社に依頼しましょう。
壁紙をリフォームする際の注意点
- エアコンを交換する前にリフォームしない
- できるだけまとめてリフォームする
- 大きな柄物は広い面積で使用しない
壁紙のリフォームする際には上記の3点に注意しましょう。
エアコンを交換する前にリフォームしない
エアコンを交換するとき、古いものよりも小さなエアコンを付けてしまうと壁紙のない部分が見えてしまいます。せっかく壁紙をきれいにしても、古いエアコンの跡が見えては台無しです。
エアコンが古くなってきて交換する可能性があるならば、先にエアコンを新しくしてから壁紙をリフォームしてください。

エアコンの交換はもう少し後にしたい、先に壁紙をリフォームしなくてはいけない。そんな場合は、別途費用が発生しますがエアコンを取り外してもらってからリフォームしましょう。
できるだけまとめてリフォームする
壁紙を新しくすると、古い壁紙が目立つようになります。例えば、玄関の壁紙を新しくしたのにリビングの壁紙が古いままだと、汚れや劣化が際立ってしまうのです。

壁紙はできるだけまとめてリフォームするようにしましょう。
大きな柄物は広い面積で使用しない
輸入壁紙には、おしゃれな柄物デザインがたくさんあります。海外のインテリアのようになるため人気がありますが、貼る部分には注意が必要です。
大きな柄物の壁紙は圧迫感があるため、広い面積に貼ると狭く見えてしまいます。

大きな柄物の壁紙を使うなら、アクセントクロスとして部屋の一面だけに貼ったり腰壁と合わせたりするといいでしょう。
リフォームにあたって押さえておきたい壁紙の選び方
ベースカラーを決める
家全体の統一感を意識する
アクセントカラーを取り入れる
壁紙選びで失敗しないためには、まずはベースカラーを決めましょう。ベースカラーは内装全体の70%ほどを占めるインテリアのベースとなる色で、壁紙や床などに使います。
ベースカラーはメインカラーとの相性を考慮しましょう。メインカラーは内装全体の20〜30%ほどを占める色で、大きな家具や家電の色に使用します。

リフォームの場合は既に家具家電があるケースがほとんどだと思うので、メインカラーに合わせて壁紙の色(ベースカラー)を選ぶといいでしょう。また、1部屋だけではなく家全体の統一感も意識するのがポイントです。
さらに、内装のアクセントになるようなアクセントカラーを内装全体の10%ほどに取り入れると、おしゃれさがアップします。
まとめ
玄関リフォームの費用相場は広さにもよりますが、おおよそ6畳で4〜5万円で依頼できることが分かりましたね。しかし、グレードが高くなると6畳でも6〜7万円と高値になるので注意が必要です。
さらに、リフォームに必要な費用に限らず、古い壁紙を処分する場合は処分費用もかかるので、予算はなるべく厳しくしすぎないようにするのが重要でしょう。
DIYも良いですが、壁紙を隙間なく埋めるには技術も必要なのできれいにリフォームしたいなどのこだわりがある人はリフォーム会社に依頼する方が安心です。

・本記事の内容は、本記事内で紹介されている商品・サービス等を提供する企業等の意見を代表するものではありません。
・本記事の内容は、本記事内で紹介されている商品・サービス等の仕様等について何らかの保証をするものではありません。本記事で紹介しております商品・サービスの詳細につきましては、商品・サービスを提供している企業等へご確認くださいますようお願い申し上げます。
・本記事の内容は作成日または更新日現在のものです。本記事の作成日または更新日以後に、本記事で紹介している商品・サービスの内容が変更されている場合がございます。
・本記事内で紹介されている意見は個人的なものであり、記事の作成者その他の企業等の意見を代表するものではありません。
・本記事内で紹介されている意見は、意見を提供された方の使用当時のものであり、その内容および商品・サービスの仕様等についていかなる保証をするものでもありません。


